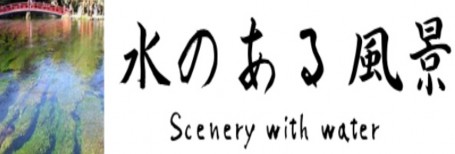8月22日、「おどけ池」散策を済ませ同市内書上公園の一画「男井戸」を散策しました。

この湧水もまた、あまが池の伝説と深く関わる逸話が伝えられています。その名の通り、湧水あまが池の「男」の対として存在するとされる湧水です。あまが池の悲しい伝説と合わせて語られることが多いです。* あまが池の悲劇と男井戸の誕生:大干ばつの際、村を救うために人身御供となった娘「おあま」が、身を投じたのが現在の「あまが池」です。「おあま」の入水により水が湧き出し、村は救われました。しかし、この悲劇を悲しんだ村人が、「おあま」の魂を慰め、また二度とこのような悲劇が起こらないようにとの願いを込めて、**あまが池とは別の場所に掘った(あるいは湧き出た)のがこの「男井戸」**だと言われています。* 対の存在としての役割: その名前は、悲劇のヒロインである「おあま」を連想させる「あまが池」に対して、その悲しみを乗り越え、力強く水を供給し続ける存在としての意味合いが込められていると考えられます。陰と陽、女性と男性といった対比で、この二つの湧水が語り継がれてきたのでしょう。男井戸の水は、あまが池の霊水と共に、地域の生活を支える重要な水源として利用されてきました。 * 水神信仰と感謝:あまが池と同様に、男井戸もまた、水に対する人々の感謝と信仰の対象でした。水神様が祀られ、地域の人々によって大切に管理されてきた歴史があります。干ばつの苦しみを知る人々にとって、湧き出す水はまさに「命の恵み」であり、その水を守り、感謝する心が代々受け継がれてきたのです。男井戸は、あまが池の悲しい伝説の背景にある、人々の水に対する切実な願いと、それに応えようとする地域の営みを今に伝える湧水です。二つの井戸の存在は、伊勢崎の地で水がどれほど重要であり、また人々がどれほど水に感謝し、畏敬の念を抱いてきたかを物語っています。