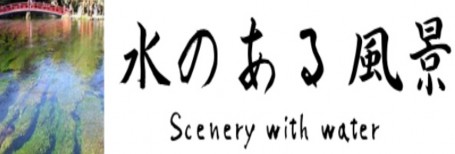先日(8月23日)木曽三社神社⛩️へ寄ってみました。

木曽三社神社の境内の湧玉 :神社の境内にある湧水で、地域の名水として知られています。 赤城山周辺の湧水は比較的軟水「地中から砂を巻き上げて湧き出すのが特徴「玉の様に水が湧く」ことからその名がつけられた様です。✴︎木曽三社神社の「湧玉(わくだま)」は、赤城山麓でも最大級の湧水として知られ、多くの逸話や信仰が伝えられています。縄文時代からの聖なる水、木曽三社神社のある赤城山南麓は、縄文遺跡が非常に多く発見される地域です。その大きな要因の一つが、赤城山が育んだ豊富な湧水であり、この水が「湧玉」と呼ばれています。縄文時代の人々も、この湧玉を生活の重要な水源として利用し、また神聖な水として崇めていたと考えられています。何千年も前から人々の暮らしを支え、信仰の対象となってきた水である、という歴史的背景そのものが、湧玉の持つ大きな逸話と言えるでしょう。玉のように湧き出る水の様子「湧玉」という名の通り、この湧水は地中から砂を巻き上げながら、まるで玉が湧き出るかのようにこんこんと湧き出しています。その神秘的な様子は、古くから人々の心を捉え、特別な力を持つ水として認識されてきました。✴︎宮内省御用生州としての歴史:明治時代には、この湧玉の水が「宮内省御用生州(ごよういけす)」として利用されていたという逸話があります。利根川で獲れた鮎をこの湧玉の清らかな水で清め、天皇に献上していたと伝えられています。これは、湧玉の水の清らかさと品質が、国家レベルで認められていたことを示す証拠であり、その特別な価値を物語っています。✴︎木曽義仲と勧請の伝説:木曽三社神社自体には、木曽義仲(源義仲)の遺臣が、義仲が討たれた後に信濃国筑摩郡の岡田、沙田、阿礼の三社を勧請して創建したという伝承があります。湧玉そのものとの直接的な逸話ではありませんが、この神社が歴史的な背景を持つ中で、清らかな湧水が重要な役割を果たしてきたことは想像に難くありません。これらの逸話や歴史は、木曽三社神社の湧玉が単なる湧水ではなく、地域の人々の生活、信仰、そして歴史に深く根ざした、特別な存在であることを示しています。