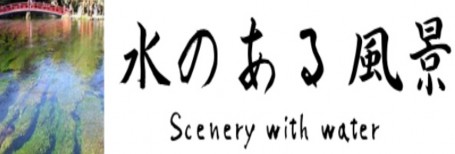昨日(9月3日)前橋から太田までドライブして来ました。目的は東毛の湧水散歩!真っ先に矢太神沼へ向かいました!
新田の荘遺跡(矢太神水源)
矢太神沼(やたがみぬま)は、単なる沼ではなく地域の歴史、特に新田荘(にったのしょう)の発展と水利権をめぐる重要な場所であり、国指定の史跡「新田の荘遺跡(矢太神水源)」の一部となっています。関連の物語・伝説は、一般的に広く知られているものは少ないですが、周辺の歴史的背景や、隣接する**「矢太神水源(やたがみすいげん)」**にまつわる情報から、その逸話を読み解くことができます。1)矢太神沼と矢太神水源の逸話・背景矢太神沼は、隣接する矢太神水源から湧き出した水が流れ込む沼で、一級河川石田川の源流となっています。この地域は、平地では珍しく湧水が豊富で、古くから人々の生活を支えてきました。2) 新田荘の水利と争い:新田荘は、鎌倉時代から多くの荘園領主が複雑に絡み合った地域であり、水の確保は農業(特に水田稲作)にとって死活問題でした。その為湧水や用水路をめぐる水争いが頻繁に発生していました。3)大館氏と岩松氏の争い: 特に有名なのは、新田氏の一族である大館宗氏と岩松政経が、「一井郷沼水」(現在の重殿水源(しげどのすいげん)と考えられているが、矢太神水源も同様の争いの対象となった可能性は高い)の用水をめぐる争いを鎌倉幕府に訴え出て裁決を仰いだという記録が残っています。矢太神沼もまた、このような水争いの舞台となった可能性が高く、水をめぐる人々の知恵や葛藤の逸話が伝えられていたかもしれません。 4)水神信仰と雨乞い:水は人々の生活に不可欠であると同時に、時には干ばつや水害といった災厄をもたらす存在でもありました。その為、湧水や沼地には水神様が祀られ、信仰の対象となっていました。 5)雨乞いの神事: 矢太神水源(矢太神沼に隣接)では、渇水時に大根神社に伝わる雨乞いの神事にまつわる御輿を沼に投入するという風習が今も残っています。これは、水不足に苦しんだ人々が、沼の神に雨を乞い、水を恵んでくれるよう祈願した切実な思いを伝える逸話と言えます。 6)「神沼」の由来: 矢太神沼の「神沼」という名称自体が、この沼が単なる水たまりではなく、神聖な場所として、あるいは水神様が宿る場所として畏敬の念をもって扱われてきたことを示唆しています。沼に住む龍神や蛇神の伝説、あるいは沼を汚してはならないという禁忌などが伝えられていた可能性もあります。7)生態系と古代の面影:矢太神水源や矢太神沼は、平地では珍しく湧水が豊富で、ニホンカワモズクなどの珍しい水生植物が生息しており、**「過去の海の名残」**があるとも言われています。これは、この場所が太古の時代から水に恵まれてきたことを示唆しています。8)千五郎池と新田開発: 矢太神沼の東には、江戸時代の代官「本間千五郎」が湧水を開削し、上江田北部(東田)に水を引いたという**「千五郎池」**があります。これは、江戸時代においても、この地域の湧水が新田開発に利用され、人々の暮らしを豊かにするために尽力した人物の存在を伝える逸話です。矢太神沼は、現在では周辺が史跡公園として整備され、歴史的・自然的な価値が再認識されています。これらの背景にある水利をめぐる争いや、水神への信仰、そして地域の人々が水を守り、活用してきた知恵と努力が、この場所の持つ真の逸話と言えるでしょう。