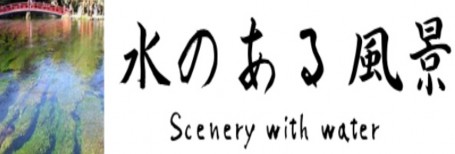昨日(9月6日)は、我郷土前橋が“水と緑と…”をスローガンとしていることから、特に印象深い利根川から市中に流れる“広瀬川”を確認しようと”臨江閣”へ向かいました。

前橋の迎賓館
1.臨江閣の存在: 明治時代の前橋市を象徴する重要な迎賓館です。その代表的な水辺の景観の一つである前橋公園や利根川のほとりに位置し、前橋のアイデンティティ「水と緑と詩のまち」を象徴する存在です。臨江閣の「江」とは大きな川を意味し、すぐそばを流れる利根川を指しています。その雄大な流れや、妙義山、浅間山を遠望する風光明媚な場所に位置しているわけです。2. 水の都・前橋の象徴: 前橋市は、利根川やそこから引き込まれた広瀬川など、市内に張り巡らされた水路によって古くから「水の都」と呼ばれてきました。3. 日本庭園の水の役割: 臨江閣に隣接する日本庭園は、池泉回遊式という様式で造られており、庭の中心には美しい池があります。この池には小川のせせらぎが流れ込んでおり、水の流れが庭園全体の風景に動きと癒しを与えています。前橋の豊かな水資源を活かした景観づくりの一環であり、臨江閣の建物の美しさを引き立てる重要な要素となっています。単に川のそばに建つ建物というだけでなく、その名称、立地、そして庭園の構成そのものが、前橋市の「水」とのつながりを深く物語っています。次世代へ繋ぐ重要な文化財として、末長く残していきたいですね。
臨江閣物語
臨江閣は、当時の県令楫取素彦(かとりもとひこ)の呼び掛けで地元財界人有力者・企業等の寄付をもとに明治17(1884)年9月に建てられたものです。主に3つの建物から構成され、利根川の流れに面し、妙義、浅間の各山々を遠望する敷地の中央に建設されました。主な構成は1. 本館と茶室(明治17年・1884年):費用は、初代前橋市長となる下村善太郎をはじめとする地元の有力者や市民からの寄付によって賄われました。特に、当時前橋の主要産業であった製糸業で財を成した商人たちが、県都としての前橋の発展に貢献したいという強い思いから官民一体となって街づくりを進めた歴史を今に伝えています。2. 別館(明治43年・1910年)明治43年に前橋市で開催された、大規模な博覧会「一府十四県連合共進会」の貴賓館として建てられました。• 国指定重要文化財: 本館・別館・茶室の3棟すべてが、平成30年(2018年)に国の重要文化財に指定。•一般公開・無料開放開・多目的利用: 無料見学以外に会議や結婚式、写真撮影など、市民が利用できる貸館施設としても活用され、郷里の詩人・萩原朔太郎も別館で結婚式を挙げていたといわれます。(住所:前橋市大手町3丁目15-3)